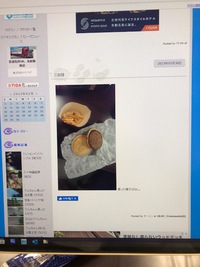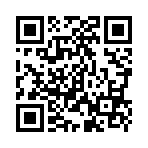2010年03月16日
石平教授講演会

中国の高度経済成長は、主に固定資産と輸出という「二台の馬車」に牽引されてきた。しかし今、その両者の失速に歯止めがかからなくなっている。表向きの成長率こそ安定しているものの、経済は安定していないのだ。
昨年は57兆円の財政出動、今年に入って105兆円という巨額の新規融資がなされたものの、その中のかなりの額が実体経済ではなく固定資産投資に流れている。表面上は不動産バブルに沸いているが、これは金融緩和・放漫融資に他ならないのであって、そのツケは必ず訪れる。
また世界金融危機、リーマンショックのあおりで中国の中小企業の40%が倒産した。対外依存率が異常に高い中国は海外、特にアメリカの影響をまともに受けてしまう。購入した多額の米国債を処分しても、それでドルが暴落すれば自分の首を絞めることになる。
高成長にかかわらず、消費者物価指数も上昇しない。満足な社会保険制度がないため、万一に備えて貯蓄する人が多く、内需拡大の足かせになっている。慢性的デフレ状態の一方、豚肉や卵など一部商品ではインフレ再燃の兆しが見えている。鉄鋼やセメントの消費はすでに伸び悩んでいるのに、なおも生産を続ける「産能(生産能力)過剰」も問題だ。
中国の高度経済成長を支えてきた要素はもはや存在しない。だが好景気の時でさえ大卒の3割が就職できなかった中国が、低成長に耐えられるとは考えられない。絶対死守ラインとされてきた経済成長率8%「保八」もすでに割り込む状態だ。
加えてインターネットの急速な普及により、中国に初めて「世論」が形成されつつある。ネット上のバッシングを恐れて党が路線を変更するなど、従来は考えられなかった現象だ。
現国家主席である胡錦涛は、2012年に任期を終える。胡には鄧小平というカリスマの後押しがあったが、ポスト胡錦涛にはそれも期待できない。民主的な選挙制度のない中国で、政府や党への不満が爆発すればどうなるか。2010年の上海万博、2012年の権力委譲を経て、多くの火種を抱えた中国が動乱期に突入する可能性は否定できないだろう。
Posted by ヤーレン at 21:15│Comments(0)